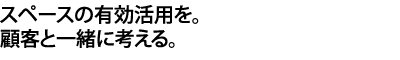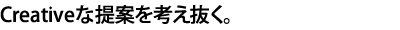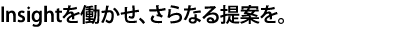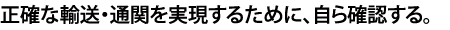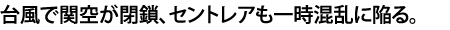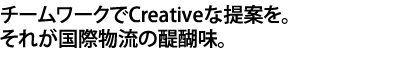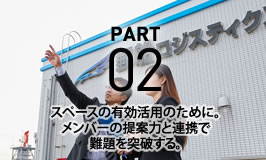PART 2 スペースの有効活用のために。メンバーの提案力と連携で難題を突破する。
愛知県を中心とする中部地区は、大手の航空機部品メーカーと関連の部品加工メーカーが集まり、全国の航空機部品の5割を生産している。日本における航空機産業の一大集積地だ。
アメリカの航空機メーカー・X社も、機体の部品の約35%を中部地区で製造している。そのⅩ社の主翼や部品の製造をしているのが、大手航空機部品メーカー・Y社だ。そして、Y社が製造した部品を、X社のアメリカ工場に届けるための全プロセスに携わっているのが、郵船ロジスティクスなのである。

X社は特殊形状の航空機部品の輸送に関して、自前の貨物専用チャーター機を保有している。機数は2018年現在、全世界で4機のみだ。それぞれにフライトスケジュールが組まれているが、日本では中部国際空港、通称セントレアでしか発着しない。その機体に様々な部品が搭載され、アメリカで組み付けられ、航空機へと製品化される。
当初、Y社が製造した部品は通常の旅客便によって輸送されていた。しかし運航を続けるうちに、チャーター機のlower lobe(ローアー・ローブ)、すなわち“お腹”にあたるスペースを有効活用し、効率の良い輸送を検討している、との相談を受けたのだ。そこでまず問題が立ちはだかった。貨物専用チャーター機は気圧のコントロールができず、可燃性のものでは運べない。通常段ボールや木箱で輸送することが多く、梱包の方法を考えなければならない。そこで、X社は特殊なアルミのケースを用意し、問題はクリアしたと思えた。しかし、もう一つの問題が浮上した。「カーゴラベル」だ。
「通常、航空貨物には貨物を識別・特定するために、紙でできたカーゴラベルを貼る必要があります。しかしながら、X社のチャーター機は旅客便ではないので、コックピット以外は気圧調整がされていません。そのためカーゴラベルのように可燃性のものを貼付すると、火災の危険が出てきます」(長田)
「直接貼らない方法を考える必要がありましたが、私たちにも『貨物にカーゴラベルを貼らないなんてあり得ない』という既成概念から抜け出せず、なかなかアイデアが出てこなかったのです」(玉城)




カーゴラベルを貼る「目的」は前述の通りだ。では、「誰が」カーゴラベルを見るのだろうか。フライトまでのプロセスで、なぜカーゴラベルが必要なのか、航空輸送業界での常識とも言えるルールを根底からメンバーは考えることになった。
「まず部品メーカー・Y社が製品を指定のアルミケースに梱包します。『指定倉庫からピックアップをお願いします』という連絡を受け、私たちが配車の手配を行い、セントレア構内にある自社倉庫に運びます。通関業務を終えた後、貨物はチャーター機への搭載を専門に行うグランドハンドリング会社の倉庫に移動。カーゴラベルのチェックを受け、チャーター機に搭載される、という流れです」(纐纈)
つまり、カーゴラベルを見るのはグランドハンドリング会社なのだ。


「彼らが搭載する手前の段階で識別できれば問題は生じません。ならば、識別を終えたカーゴラベルを搭載前に剥がし、可燃性のものがない形でチャーター機に搭載すればいいわけです。『直接貼るのではなく、箱をラップで包んでその上からカーゴラベルを貼り、搭載前にラップごと一気に剥がしてしまう』というアイデアが生まれました」(守田)
ちなみにここで使うラップは業務用の大きなサイズのものだが、材質は家庭で使われるそれと同じ。上乗せされるコストは無視できるレベルだ。郵船ロジスティクスの業界の常識を変えるとも言える提案を、X社は快諾。問題は無事に回避され、以後Y社製品のチャーター機への搭載は、ラップにカーゴラベルを貼った形で行われることになった。


そしてプロジェクトのメンバーは、出荷を進める中、さらなる提案を思いついた。それはアルミケースにかかる関税のカットである。
「4機あるチャーター機は、全世界の輸送で使われています。同様に、搭載するアルミケースも“リターナブルケース”として世界中で使われているのです」
アメリカの工場に運ばれたケースは、現地で製品を下ろした後、空(から)の状態で日本に送り返され、一定の保管期間を経てまた製品を積めて輸出する、という流れになる。X社にとっては単なる返送作業だが、関税法の視点からは「日本への輸入」であり、3%の関税対象だ。
しかし免税を受ける方法がある。それにはすべてのケースの移動に常に履歴をつけ、「日本とアメリカでまったく同じシリアルナンバーのケースが行き来している」と、証明できること。この管理がしっかりできていれば免税が可能となり、X社にとっては大きなコスト抑制につながるというわけだ。お客様目線で考え続けたからこその提案となった。
言うは易し、行うは難しだ。管理をしっかりするには、郵船ロジスティクス内で輸出カスタマーサポートと輸入カスタマーサポートの緊密な連携が確実になされなければならない。それでもX社という顧客のコスト抑制につなげるには、自分たちが動くしかないのだ。
「具体的には、アメリカから送り返されてきたケースを視認することです。到着に合わせて私や他のメンバーが倉庫に出向き、アメリカからのインボイス(出荷書類)にあるナンバーと、目の前にあるケースのシリアルナンバーを対査(照らし合わせること)します。同じものが来ているかを自ら確認します。通常の貨物であればグランドハンドリング会社が行う仕事ですが、この案件についてはケースにカーゴラベルがないため、私たちが責任を持って行うのです」(長田)
「部品メーカーのY社様から『このナンバーのケースを、日本からの輸出用に出した』という連絡を受けたら、そのナンバーを確実に作業員に伝え、倉庫で視認してもらいます。そして、輸出手配が完了したことを輸入カスタマーサポート課(長田さん)に伝えます」

それでも思わぬ事態は発生する。2018年9月、台風21号が西日本を直撃し、関西国際空港(関空)が閉鎖。関空の貨物を一時的にセントレアへ避難させる事態に陥り、セントレア構内の倉庫という倉庫が埋まっていったのだ。アメリカから送り返されてきたこの大きなケースを、どこに置けばいいのか…。まずは、自分たちにできることをやろう。輸出カスタマーサポートと輸入カスタマーサポートが連携をとって状況を共有、協力会社に片っぱしから連絡をとり、保管できる倉庫をなんとか確保した。後日、顧客に当時の経緯を説明したときには、感謝の言葉をもらったという。
「X社の日本拠点の物流担当者は、日本で行われる物流のすべてを管理しています。常に手一杯の状況ですから、私たちにできるサポートを追求し、改善策を提案・実行していきたいと考えています」(守田)

郵船ロジスティクスの存在は、もはやサポートの域を超え、X社と伴走するパートナーと言えるだろう。X社の仕事に携わることに誇りを持ち、プロジェクトメンバーを率いる守田はその醍醐味を語る。
「国際物流の面白いところは、プロジェクトに合わせて独自の提案ができる点です。そもそも物流は決して個人プレーではできない。営業、そして輸出・輸入のプロセスに携わる全てのメンバーが、職種から文化、考え方までお互いのバックグラウンドの違いを超えて、協力と調整を行います。その中で、そのプロジェクト独自の提案が生まれてくるのです。協力会社、そして国際的なネットワークというリソースをどう使うかによって、お客様にとっての最適なサービスの提案はそれぞれです。その提案力を磨けることが、郵船ロジスティクスの仕事の醍醐味ではないでしょうか」